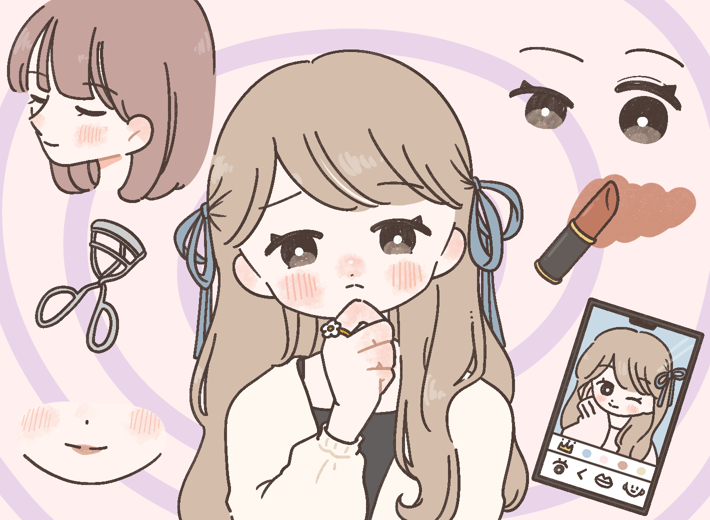大阪大学教授で、顔に執着する現代人の心理を科学的に解明した『顔に取り憑かれた脳』(講談社現代新書)の著者、中野珠実さんに、加工アプリを使いすぎる理由や、自分の顔をもっと魅力的に見せるための方法を伺いました。
人はみんな「顔」が好き

——そもそも、人の「自分の顔を加工してよく見せたい」という気持ちはなぜ生じるのでしょうか。
人はみんな顔が大好きです。近赤外光を使って人の視線の動きを観察した実験では、人は映画やテレビを見ているとき、背景の風景はほとんど見ず、人の顔ばかりに視線がいくことがわかりました。
中でも「自分の顔はVIP扱い」です。みなさんも、集合写真や卒業アルバムで、自分の顔だけはすぐ見つけられるのでは。MRIを使った実験でも、人は他人の顔写真より、自分の顔写真を見ているとき、脳の伝達物質「ドーパミン」が分泌されることがわかっています。
生きるために自分の顔を“VIP扱い”している
ドーパミンは自分にとって価値ある「報酬」がもらえそうなときに分泌されるもの。
分泌されると「その情報にもっと注意を払って」「その情報をもっと収集して」という指令が脳の各所に伝わり、その結果、人は「報酬」をもらうためによりよい選択をしたり、行動をとろうとします。
自分が価値を感じる「報酬」をもらうことは、自分の生存確率を高めるという根源的な欲求にもつながります。自分の顔の情報を集めて、より魅力的に見せようとするのもそのための手段のひとつといえるのです。
写真加工で多めに出る「ドーパミン」、ギャンブル同様の依存も

実はドーパミンは、覚醒剤やコカイン、アルコール、ニコチン、ギャンブルやゲームなどの依存にも関わっています。
ドーパミンは、私たちが鏡や写真で自分の顔を見るたび分泌されますが、顔にあまり変化がなく飽きてくると分泌されにくくなります。しかし加工やメイクなどで顔が魅力的に変化すると多めに分泌されます。
加工自体は自分をよりよく見せたり自信をつけたりするための前向きな行動なのですが、繰り返すうちに依存的となり、加工がエスカレートしてしまうこともあるのです。
“盛りすぎ加工”した顔は人を“不安”にさせる
人は「人間の顔とはこういうもの」という基準があり、その範囲内の顔を見ることで安心します。
30人の女子大生を対象にした実験で、自分を含む全員の顔写真に、顎を細く、目を大きくする加工を1〜8段階に施した写真のセットをつくり、見てもらったところ、中くらいに加工された3〜5段階に加工された写真がもっとも魅力的と感じるという結果が出ました。極端に加工された7〜8段階になると、好感度は大きく下がりました。
またあるロボット工学者によれば、人は人間とかけ離れた姿のロボットを見たときは、ロボットだとわかるので不安は感じませんが、ロボットの見た目が人間に似れば似るほど、人間とのわずかな違いに『何者かわからない』という不安、拒絶の感情を持つそうです。
加工しすぎで目鼻立ちのバランスが悪い加工写真を見たときにも、人は同じように感じるのかもしれません。
加工しすぎる人は“細部にこだわりすぎる”性格

——自分の顔写真を加工しすぎる人にはどんな特性があるのでしょうか。
「細部に注意が向きやすい」という特性があります。
パーツだけを見て「もっと目を大きく」「鼻を細く」など細部にこだわる人は、「全体的に見るとどうなるだろう」と「他人が見たらどう思うだろう」といった想像ができず、依存的に加工し続け、どんどんバランスの悪い顔写真をつくることになっていくのです。
表情や角度を“少しだけ”変えると、魅力的に映る
——脳科学を利用して、SNSなどでより自分を魅力的に見せるための方法はあるのでしょうか。
実は、大事なのは顔の表情や動き。人間の脳は、目から見える情報をずっとキャッチしていますが、全てを処理するとパンクしてしまうので、動いたり変化したところだけを処理します。
ですからいつも同じ表情や角度の写真ばかりを投稿していると、見ている人は予測がついてしまい、脳がスルーするので興味を持たれなくなるかもしれません。いつもと違ったアングルの写真や、話したり動いたりしている動画を投稿して、見る人の予測を少しだけ裏切っていくと、魅了できると思います。
ただし、あまりにも大きい変化だと人を不安にさせてしまうので、ポイントは“少しだけ”変えること。普段と違ったアプローチで自撮りすることで、表情や動きの研究にもなりそうですね。
きれいな顔を見すぎると“自分の顔”に満足できなくなる
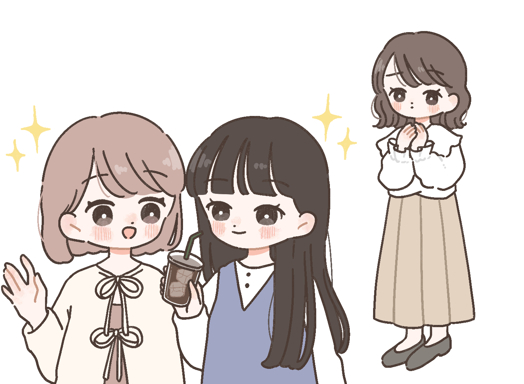
——日本に鏡が登場したのは平安時代。そこから人は自分の顔を気にし出したのだとか。今はスマホで気軽に自撮りやSNS投稿ができて便利な反面、自分の顔にしばられすぎる人も多いのでは。
オランダの研究グループが若い女性を対象に行った実験ですが、加工なしの人の写真ばかりを見せたグループと、美しく加工した人の写真ばかりを見せたグループとでは、後者のグループの人たちの“自分の容姿に対する満足度”が下がってしまったそうです。
人間はどうしても、他者と自分を比較することで自分の価値を決めがち。そして他人と比較するのに一番わかりやすいのが顔なのです。とくに日頃からSNSや動画で外見のいい人を見て自分と比較している人は、自分の顔に執着しやすい傾向にあると思います。
「自然」や「アート」がこだわりを手放すための救世主

——顔への執着から解放されるにはどうしたらいいのでしょう。
人と自分を比べるのは仕方ないことですが、自分の外見が気になってしょうがない人は、“暇”という可能性もあります。“自分の中の自分”と対話をしすぎているのです。自然やアートを見るのがいいかもしれません。そうしたものに畏怖を感じると、自分の価値(優先度)が低くなり、こだわりがどうでもよくなるといわれています。
また顔以外のことも比較対象にしてみては。自分を構成しているのは顔や外見だけなく、これまでの経験や仕事、能力、環境、趣味、思い出など複数の要素があります。大学生なら勉強や部活、バイトになどに打ち込むのもいいですよね。
本当はみんな、顔より「心」を見たがっている
決して美人とはいえなくても、モテる人、人気がある人はいます。そういう人は人間的な魅力があり、自信が顔にも現れるのだと思います。
人間は顔に興味がある生き物だという話をしてきましたが、それは、社会的な生き物だから。つまり顔に興味がある人は社会性が高い人ともいえるのです。ただ、結局はみんな、顔を媒介して“心の状態”を見たがっているんですね。
加工など手っ取り早く顔を変えられる手段は、のめり込むのではなく賢く活用して、人間性や能力を磨くことも意識するといいかもしれません。それが周りの人に一歩リードした美しさを手に入れられ、年を重ねても輝き続けられる方法なのかも。