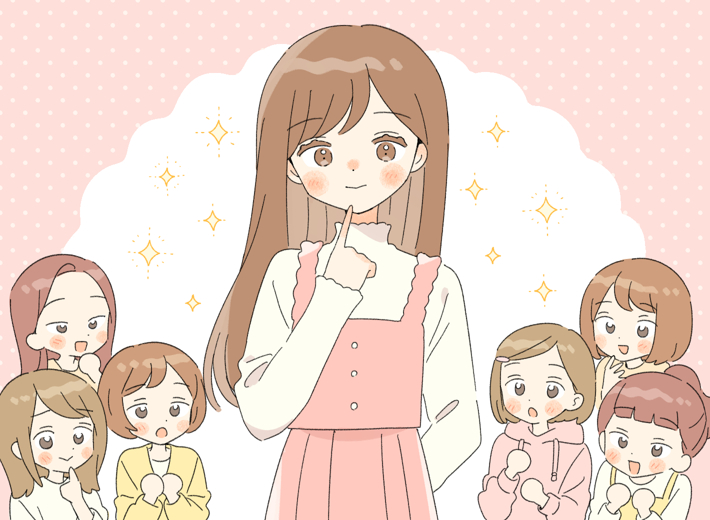顔や見た目の研究をしている、心理学者の山口真美先生にインタビュー。より自分らしくヘルシーな人間関係を築く方法についても、話を聞きました。
かわいい子のそばにいると“得”をする

――女性は、「友だちはかわいい子のほうが得」と思って友だちを選ぶ人も少なくないように感じます。心理学的に見て、この現象はどういうことなのでしょうか?
認知心理学では、「チア・リーダー」効果が知られています。一人で写った写真よりも、かわいい子と一緒のグループで写った方が、魅力的に見えることが実験で明らかになっています。
たとえば、美人コンテストで順番に点数を付けていきますよね。最初に美人が登場すると、その人が基準となって、あとから出てくる人の点数が低くなりそうに思います。しかし実際には逆で、一度高い得点をつけてしまうと、その周囲の点数が高くつけられる傾向があるのです。
ここから考えると、きれいな人と一緒にいるとグループとしてのランクが上がり、一人でいるときよりも美人に見えてくることがわかっています。
――女子たちはそれに気づいているということですか?
直感的にそのほうが“自分も映える”と感じているのでしょう。美人はまわりに波及する効果があるので、自分の価値を高めるという意味で、きれいな友達を選ぶのは正解。心理学をうまく活用しているといえます。
日本人ならではの“美人度を平均化する能力”

特に日本人はその傾向が強くあって、グループでアイドルを応援する文化、いわゆる“箱推し”はその代表例です。
つまり、日本人にはメンバーの美人度を平均化する能力があるということ。美人度に差があっても、全体としてこのくらいの魅力があるというのを直感的に計算できるんです。世界的に見て、稀な能力だと思います。
――海外ではその傾向は少ないんですか?
欧米は個人主義が強いので、そもそもグループのアイドルが少ないですよね。グループだとしても、センターの一人とその他の引き立て役という構成になっていて、日本のような箱推しの現象は生まれません。
同じアジアでもフィリピンは欧米文化が色濃いので、似たような傾向にあります。韓国にもグループのアイドルはいますが、メンバー全員を美人にしているので、魅力を平均化することまではできていないと思います。
いつまでもかわいい子のそばにはいられない
――美人やかわいい友だちをつくることはメリットしかないんでしょうか?
海外では通用しないので、世界に出てみたいと思う人はきれいな友だちに頼れません。日本だとしても、社会に出ていつまでもグループにいて美人の恩恵を受けることもできませんよね。
自身の魅力を磨いて、独立して魅力を放てるよう準備しておく必要があるかもしれませんね。
女性同士の潤滑油は「かわいい」から、「みんなと同じ」へ
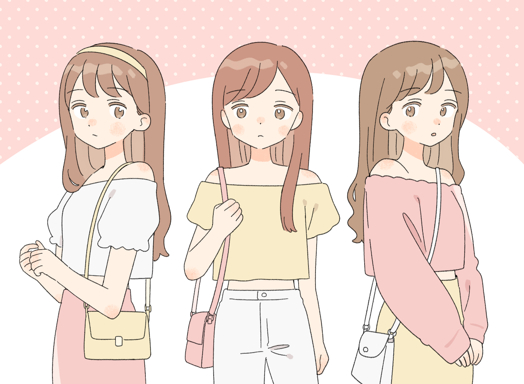
――「きれいでいたい」は女性なら誰しもが思うこと。つまり、かわいくきれいでいることは女子の友人関係を良好にするのではないかと思っています。
女性の処世術の1つではあるかもしれないですね。ただ、最近は男子学生もメイクをしたり、美容医療を経験したりというのが珍しくなくなってきました。そのなかで突出して美を追求しているような男子を見かけるようにもなっています。
そして、最近の女子学生は「きれいを追求する」というよりは「きれいでいる」ことを重視していますよね。つまり、みんなと同じでいることが大切なのかもしれません。
美しさを競わなくなった理由は「マッチングアプリ」?
――高い水準で美を追求する仲間を求めているわけではないということですか?
とにかく個性的にはしない。派手でもカラコンを入れるくらい。女子はみんな平均を気にしていて、集団のなかでどう見られるかを考えています。
“マウントを取る”というような行動をとると、女子集団からは外れていきます。特に最近の女子学生は、平和でいたいという傾向が強くなっているように思います。「競争よりも協調」ですね。リア充とかオタクとか関係なしに、皆と円滑でいようと心がけています。
それに、いまはマッチングアプリがあるので、競争することなく、平和に彼氏をつくることができますよね。ひと昔前なら、同じ学内で彼氏をつくるために、女子の間で競争が生まれていましたが、その必要がなくなったのでしょう。
――「量産型」という言葉がありますが、これを良い傾向として捉えているのに驚きました。自分自身が定まっていない学生が協調という生ぬるいプールにいるということでしょうか?
男子を奪うことで後々の友達関係にも響くと考えていて、競争するという気持ちを持ってはいけないと思っているのかもしれません。容姿にしても、個性を追求するというより、黒髪でウケのいいきれいめの格好がいい、となるのでしょう。
かわいい友だちといることで感じるプレッシャー

――きれいな友だちは自分にメリットがある反面、プレッシャーにもなりかねません。常にきれいでいなくてはならないという脅迫観念も芽生えそうですが?
その意識は薄いかもしれません。いまの学生は最低限の清潔感を保って、そこそこきれいにしていればOKと思っているのではないでしょうか。
マッチングアプリも登場して競争が必要ない世の中なので、かわいい子や美人だけがすべてを持っていくわけではありません。きれいな友だちに対しても、「見ていて気持ちいい」と一定の距離を持って接しているように思います。
すべての人の顔が“加工ありき”
――最近はSNSをとおして、より身近なインフルエンサーに憧れる傾向もありますね。
そこでおもしろいのは、インフルエンサーはリアルでものすごく美人でなくてもいいと思っているところです。その人そのものというより、加工した半分バーチャルな美人の顔で良いと考えていて、頭の中でその顔に置き換えているようにみえます。
顔の研究でいうと、きれいなものばかり見ているとそれに「順応」してしまい、実際の自分の顔とのギャップがより激しく見えてしまう傾向がある、というのが従来の見方でした。ですが、現在は自分の顔もインフルエンサーの顔も加工ありきで見ているというのがおもしろいところです。
――加工ありきの世界で納得がいくなら平和ですが、自分の顔を加工した顔に近づけなくてはと思う人も出てきそうです。
そう思って顔を変えたいと強く思う人の中には、心の問題を抱えていることがあるのかもしれません。
顔は自己の一部なので、自分に何かしら納得いかない部分があって顔を変えなきゃいけないと思い込んでいるということもあるでしょう。少しくらいならいいかもしれませんが、歯止めがきかなくなるほど変えたいと思うのは危険ですよね。
友だちの容姿に振り回されないための意識とは?

――歯止めがきかなくなるというのは、「整形沼」と呼ばれる現象ですね。かわいい友だちに影響されて顔を変えたいということもありそうでしょうか?
整形したいというときに、憧れのきれいな人に近づけたいのか、平均顔に近づけたいのかということです。
整形はマイナスをプラスにするイメージで、ちょっと目立って気になる部分を平均に近づけたいというのは、ある種、正しい姿だと思います。病気になったときに健康な体に治したいという欲求に近いので。
ただ、「◯◯さんになりたい」というのは間違った求め方なのかなと思います。
――友だちがかわいかったり、美人だからといって振り回されるのは違うと?
あくまで自分は自分です。友だちもアイドルもインフルエンサーも自分を知るための材料として考えてほしいと思います。いまの学生は競争よりも協調しすぎる点も心配です。
人と違うからこそ、魅力的なのです
整形するにしても、気になるところは友だちとは違うはずです。自分に似合わないのに友だちのコミュニティの協調に流されたり、友だちと一緒になりたいというのは違います。
顔は全員が同じにはなれません。若いうちはスレンダーな体型に憧れるかもしれませんが、女性らしい体型が似合う人もいます。体型も顔も、それぞれが人と違うから魅力的なのです。
顔も体型も自分自身のアイデンティティです。人と一緒になって、自分をなくさないようにしてほしいですね。
――ありがとうございます!