第1回は、「文化人類学的視点」からの美人論。その道の第一人者である斗鬼正一先生にあれこれと聞いてみて、「美」についておぼろげにわかってきたことがある。それは「絶対的」ではないということ。つまり……、興味が湧いてきませんか?
衣食が足りて、人はダイエットにいそしむ
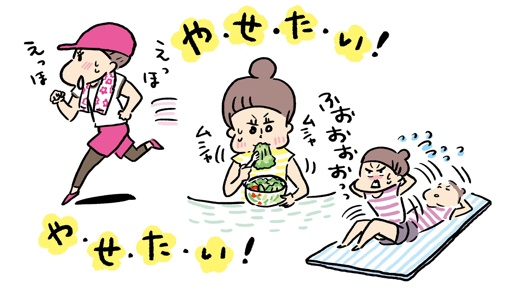
──「美人という概念は、一体どういうものなんだろう」、といった根本的な疑問は誰もが一度は感じたことだと思います。そして情報収集していわゆる「美人像」を形づくって、そこに向かって努力する。今の美に対するアクションはそんなところから始まっているように思いますが、文化人類学的に捉えた美人についてお聞かせ願えますか。
「日本ではもう何年も痩せていることがまずは美しさの条件、みたいな風潮があって、一生懸命ダイエットしたりしていますよね。それで逆に病気になってしまう人もいる。
昔のヨーロッパの上流階級の人たちは、ヨーロッパ型のコルセットを装着して、無理矢理ウエストを締め付けていた。辛くて苦しい思いをして。どちらも努力すればするほど褒められる。
でも、そうした美人像というのは、『きちんと食べられている』、『医療がしっかりしているから死ぬ恐れが少なくなっている』といった背景があるからこそ、成り立つのです。つまり、飢えることのない豊かさが、人を痩せさせたがっているわけです。
歴史を紐解いていくと、痩せていることが美人の条件であるというケースはあまりないんです」
「美人=ふくよか」が世界の多数派。
牛乳であえて女性を太らせる民族も

──確かに、太った女性がもてはやされる地域や民族というのは今でも結構あるようですよね。
「そうですね。世界では『太っている方が美人』との考えが多数派です。日本でもそういう時代はありました。平安時代の絵巻物などを見ると、どちらかと言えばふくよかな女性が多いですよね。
アフリカやミクロネシアなどの地域は、今でもそうです。言い換えれば、もともと食料が十分ではなかった地域です。そういう地域では死と隣り合わせという切実な環境下に生きてきた人も少なくない。痩せているということは、死に近いわけです。
逆に言えば、身分が高く豊かで食料に困らない人が太っていて、死からも遠い。だから自ずと太っている方が美人とされるわけです。
ですから結婚前の女性に毎日牛乳ばかり飲ませて、一生懸命に太らせるという文化を持つ地域もあるのです。太っていることは豊かさと生の象徴なのです」
人は「自然」がキライ。
「手を加えたもの」を美しいと感じる
──死というものが、美人の概念にも関わっているというのは興味深いですね。人は常に死というものを意識しないわけにはいかない。でもそれが希薄な社会状況になると、その概念も変わってくるんですね。
「人にとって生きることこそ最も重要なんです。死の手前には『病気』がありますね。それらはすべて動物的であり、ごく自然なことでもあります。
でも人間というのは、この『自然なこと』が大嫌いなんです。死や病気は嫌い、怖い、醜い。つまり美の対極なんです。さきほどの一生懸命太らせるというのも、自然なことではありませんよね。
化粧もそうです。化粧はきれいになるためのもの、となりますが、具体的に考えていくとわかってくる。皺を隠す、しみを消す、白髪を染める。つまりそれらは老化への抵抗なんです。そしてその老化の先には死がある。化粧というのは死に対する対抗手段でもあるんです。
さらに、整形という身体変工をする人もいる。死や老化など、つまり自然であること、すなわち動物的であることは文化的ではない、美しくないんです」
──自然よりも手が入ったもののほうが文化的であり、人間は好むということですね。
世紀末的な不安感は
「病的な美人」を生み出す

「アマゾンの地域には、口唇の下に棒を刺している民族がいます。あれもあの民族としては自然のままの身体の加工なんです。彼らは服を着ていなくても恥ずかしいとは思いませんが、棒を外した姿を見られることは、恥ずかしいことなんです。つまり、文化です。文化が加わっているものは美しく、加わっていないものは恥ずかしいんです」
──文化というのはいつの時代もどんな場所でも、人間にとっては強い後ろ盾になるというか。人間を強く動かすというか。
「でもそれが行き過ぎて、世紀末など時折気味の悪い美的価値観が出てくることもある。
幕末の歌川国貞の浮世絵はアバンギャルドでアンニュイ、神経質で体のバランスがよくない女性を描き、それが個性的で魅力があると評価された。
竹久夢二の描く明治大正期の美人像はどう見ても健康的には見えない。死に近い方が美しいという退廃的な美感です。
醜いものが美しいという価値観の逆転現象が現れるのは、そうした世紀末的な『先の見えない』不安からくるものなのでしょう」
——今も世紀末的なんですかね。血色の良くない病的なメイクが好まれたり、筋肉を落とす注射をして、肉感のない体型になりたいみたいな価値観も一部にはあるようですし。
首長族の美人の起源は「トラ対策」?
──文化的であるということは、死や病気に抗う、ということでもあるわけなんですね。
「タイやミャンマーのいわゆる首長族という民族がありますね。真鍮のリングを首につけて首を長くする、それが長いほど美しいという美意識を持つ民族です。とても長い伝統を持つ習慣です。一説には、トラが人の首を噛むことを恐れて始まったともいわれています。
ただこの伝統も今は少し変わってきています。観光客が喜ぶから、という理由でそのような姿を維持しているという面もあるのです。つまり、経済効果からです。
また、現代は情報量も多いですから、世界を知り始めた若年層の中にはそのような伝統を嫌がる人も出てきています。どちらも文化の影響といえます」
経済力の高さが「自分たちの美人」をつくる

──経済面が価値観を変えるということは多そうですね。美人という概念もそうなのでしょうか。
「最近の若い女性を中心に韓国のアイドルがもてはやされるようになってきました。国内ではなく、外のアイドルです。その一因には、日本がずっと不況で中韓などに追い越され、経済大国の座を失いかけているという経済的な面も関係していると思うのです。
また、韓国のコンテンツ産業を中心とした発展も目まぐるしいです。それらが重なっての現象なのだと思います。
面白いデータがあるのですが、韓国の場合は高度経済成長の後に好ましい顔の縦横比に変化があったのです。その時期を境に長さが少し短くなって、丸顔が好まれるようになった。これも経済力がついたことによってアイデンティティが明確になり、自分たちの文化で美の物差しがつくられた好例ではないかと考えています。
日本では昔から『秋田美人』という一つの美人像がありますね。これも様々な要因が背景にはあると思うのですが、一番大きいのが経済的な発展なのではと思っています。
鉱山開発によって経済的に豊かになり、お金持ちたちが芸者さんを品定めして選りすぐっていった。それが秋田小町の始まりだったという説があります」
「時代の権力者」が美人を決めることも
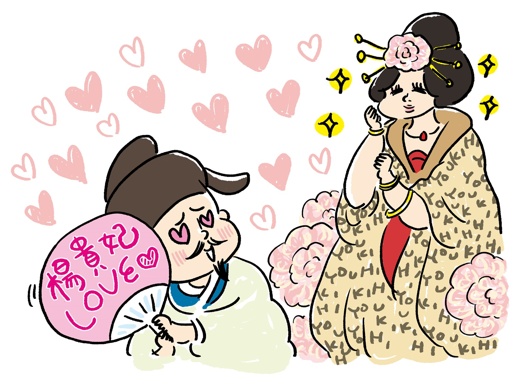
──伝統さえも経済力には勝てないことが多いのですね。それ以外に価値観を左右する大きな力ってあるんでしょうか。
「政治力ですね。平たく言えば権力者。例えば、楊貴妃はふくよかな人だったと言われていますが、それは玄宗皇帝が太めの女性を好んだからだそうです。そうするとそれは庶民にも影響を与えてしまう。それまでは痩せた人ばかり宮中にはいたのに。
日本の場合は明治政府の欧化政策、いわゆる文明開化の影響が大きいです。近代化するために欧米に倣え、伝統は切り捨てよという大きな転換策です。
技術的な部分だけではなく、やたらと欧米人の容姿にも言及した。『こういうのが美しいのだ』と。だから欧米人の姿形は急速に社会に浸透していった。でも日本人自体がすぐにそのようになれるわけではない。大きな矛盾を抱えてしまうのです。
夏目漱石の『三四郎』の中にも、熊本から東京に行く汽車の中で初めて欧米人を見て、なんて美しいんだ、と感動する場面がある。事前に情報の刷り込みがあるから、初めて見ても美しいと思えるんですね。
でも第二次大戦が始まると、それが一転する。憧れていた人たちが敵になる。逆に純粋な日本的女性が尊ばれる。丈夫な体つきで、いかにも『ニッポンのお母さん』的な女性です」
──意図的に変えられたり、変わらざるを得なかったりと。
「江戸時代は鎖国をしていたから、長崎の出島で細々とオランダと交易する程度だったと思ってる人が多い。けれどもそれは間違っていて、大陸からも北からも南からも文化は伝わってきているんです。中央から離れた地域でも交易をしていましたから、いろいろなものが日本に流れてきているのです。
浮世絵には欧米の遠近法の手法の影響が見られますしね」
一つの物差しに縛られなければラク
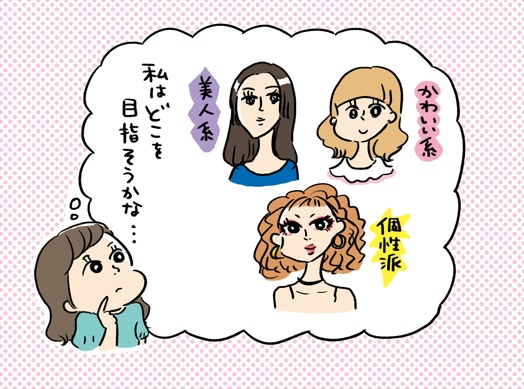
──そう考えると、有史以来日本は常に外国の影響を受けていたといってもいいですね。日本人の美的価値観は固有なもののように思われがちですけど、そんなことはないんですね。
「そうなんです。異文化にものすごい影響を受けているんです。縄文時代だって、我々が考えている以上に離れた地域同士でのコミュニケーションはありましたし、国風文化と言われる平安時代でさえ、中国の大陸文化の色は濃い。だから、日本固有の文化ってそんなにないんです。
人間は外に価値観を求める傾向がある。それは人類共通の願望でもあります。
何故かと言うと、視野が狭くなるとそれが絶対的なものであると思ってしまいがちなんです。そうなると諸々辛いことが増えてくる。今の世の中って、そういう傾向にあると思いませんか、世界的に」
──ああ、確かにそうですね。
「言い換えれば、決まった物差し一つに無理矢理合わせようとしてしまう。若いときほどついそうなってしまいがちです。日常生活でも、ファッションでも。
常識というものは、民族によって異なるし、同じ民族でも時代によって変わります。恒久的なものではないし、絶対的なものでもない。常識なんてその程度のもの、と考えられれば人生ラクになります。一つの物差しに無理矢理当てはめる必要はないんです。
でもなかなかそれも難しい。その時代の価値観、美しさを追わないというのもまた生きづらい。他人と違うということ自体を、恐怖と感じてしまう人も決して少なくない。横並びでいたいと。そのあたりのバランス感覚が必要なんでしょうね」
──いろんな物差しがある方が多様で自由な社会と言えるんですね。でもこのグローバルな社会では、その物差しが強大なものになっている感じもします。
「自分たちが決めた物差しならまだいいですけど、今はメディアや企業が価値観を決めてしまうこともある。それを必死に追うのは、あまり幸福なことではないという気がします。
物差しって時代や民族によっても変わってくる。絶対的なものではない。だからもっと気楽にしていられればいいんです、物差しに振り回されずに。
多様性や異質を認めないという傾向が強くなっていますが、それはまずい。いろいろなものに出会って、たくさん迷って、そして自分の価値観は自分で選んでいくということが望ましいと思っています。それは美に関しても同じです」
取材協力








